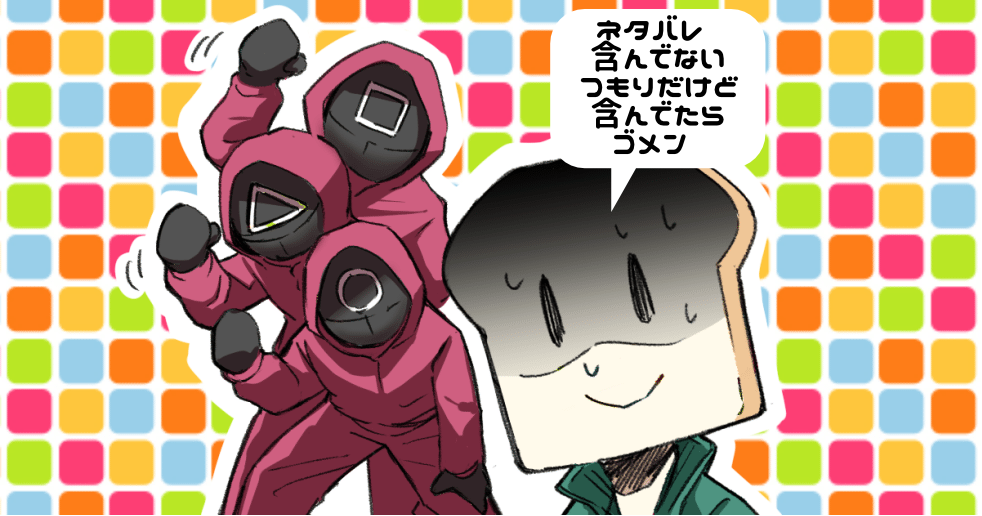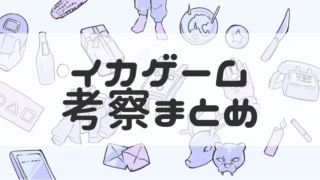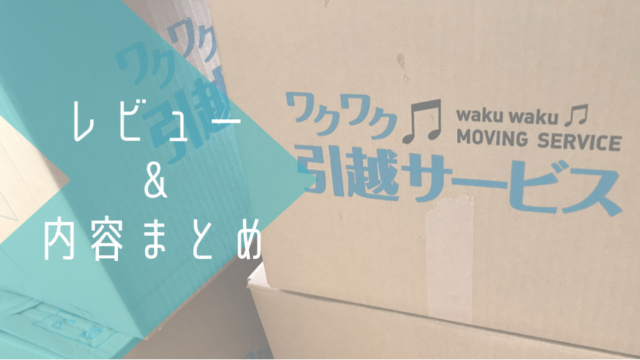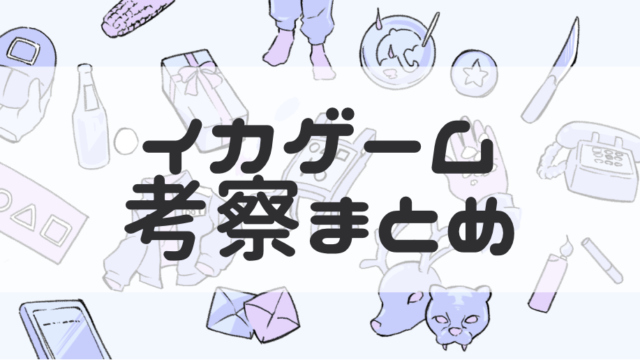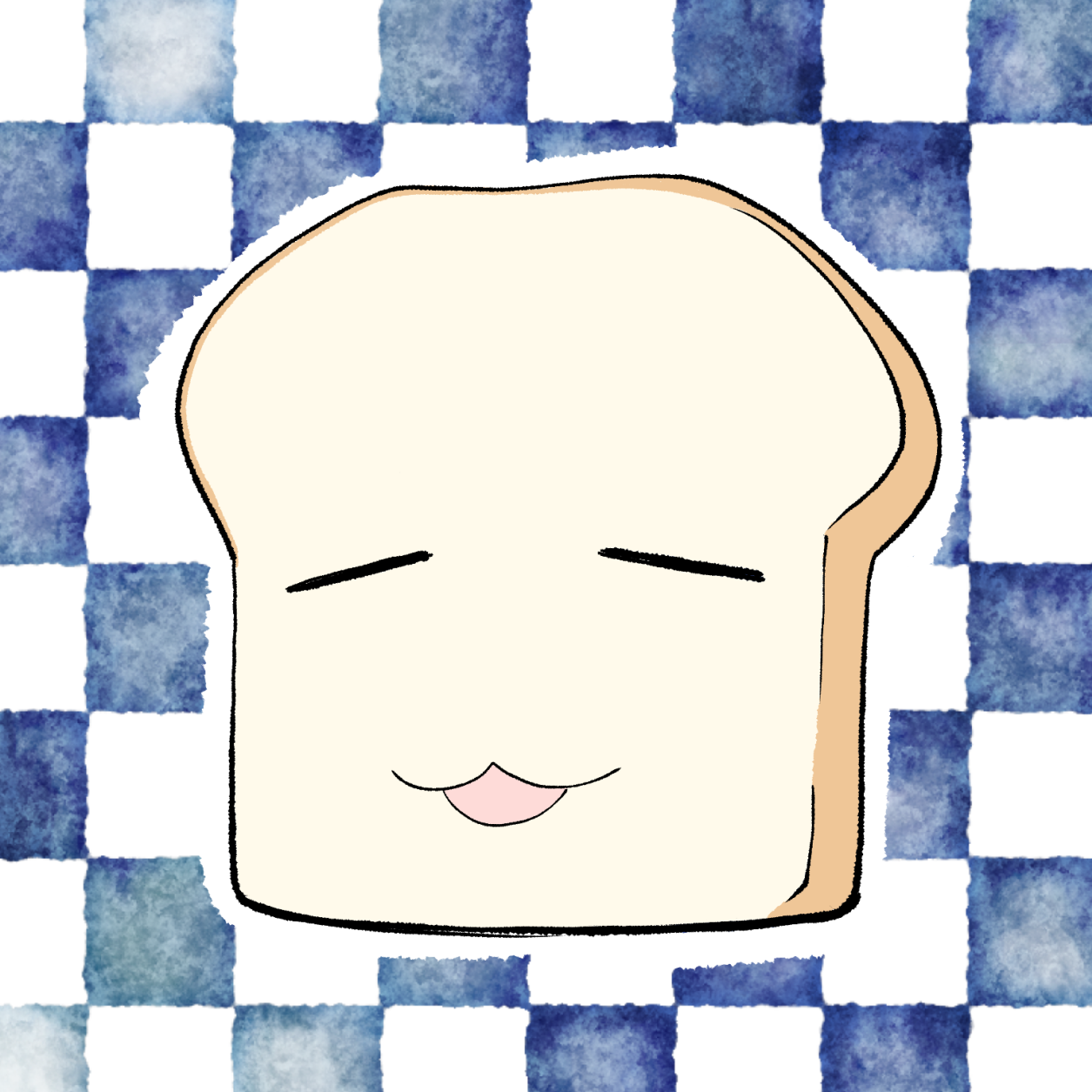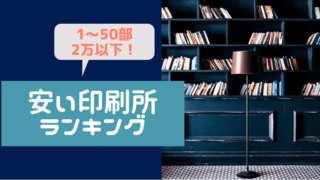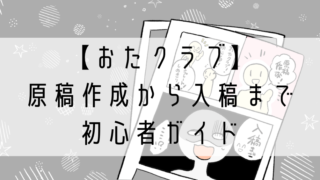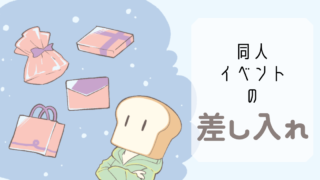ネットフリックス舐めてた。
というか韓国のコンテンツ舐めてた。
先日ちょっとしたきっかけで韓国ドラマの「ミセン-未生-」を観てからもっと他の作品も観たくなりとうとうネットフリックスを契約した。(ミセンはhuluでも視聴可)
以前CMで見てからずっと気になってた「イカゲーム」を早速視聴。
レビューも高いし期待値は高めだったのだがその数値を大きく上回り結果ドハマり。
1話につき1時間の長さで全9話という日本の連ドラのボリュームとほぼ変わらない量なのだが最終話までほとんどノンストップで視聴。
というかストップする時はお手洗いと食事の用意だけでそれ以外は常に画面にくぎ付けだった。
あまりにも衝撃的かつ引き込まれるストーリーや人間ドラマを見てこの感情をどこかに書き留めておきたくて記事を書き始めた。
イカゲームを観た人に共感してもらえたら嬉しいしまだ観てない人に興味を持ってもらえたら嬉しい。
まず、イカゲームがどんな話かというと、
多額の借金を背負った人や生活困窮者たちが456億ウォンの賞金をめぐりデスゲームをする話
である。
カイジのパクリとも言われていたのだが、個人的には韓国の社会情勢をうまーく取り入れ様々なデスゲームやマネーゲームの作品からインスパイアされて作られたものと感じた。
まずとにかく印象に残ったのは
・デスゲームにも関わらず感動させられる人間ドラマ
・欲に目が眩んだ人間の本当の顔
の部分だ。
そして
・わかりやすいシナリオ
・綿密な計算とテーマのもと作られた舞台セットと映像
この記事では個人的にここがよかったという部分を感想を交えながら綴っていこうと思う。
登場人物の掘り下げが丁寧かつ感情移入させられる

イカゲームで一番驚かされたのは、ストーリーが進むにつれ参加者同士で様々なドラマが起き、そこで細かな人間描写が現れるという部分。
この描写力がとにかく繊細。
むしろ
デスゲームがメインというより、”欲に目が眩んだ人間”と”人間らしさを忘れない人間”とのドラマがメインなのでは
と思えるほどである。
人を信じなかった者が仲間に心を開くようになったり、頭脳明晰で冷静な者が卑劣な方法で仲間を裏切ったり、それまでずっと心優しかった者が自分が不利な状況になると豹変したり、などなど登場人物の心情の移り変わりがリアルで心を抉ってくる。
そしてイカゲームの中で起きてることはまさに社会の縮図なのだと感じた。
主人公以外の登場人物のバックヤード
また別の方向で驚かされたことがある。
それは 主人公以外の登場人物にもしっかりとスポットが当たっているということだ。
本編通して主人公と深く関わる人物は数人いる。
最初に見た印象はただ個性的なキャラクターでしかないのだが、途中でそれぞれのバックストーリーの話になる。
例えば、最初「スリの女」と主人公から呼ばれるキャラクターがいるのだが、その”スリの女”がなぜスリをしなければならなかったのかという部分をとても丁寧に作っている。
主人公以外の主要人物たちにもそれぞれゲームに参加する理由がある
ということをとても丁寧に描いているので観ているこちら側も主人公以外の他の人物にも興味がわき感情が生まれてくるのだ。
ちなみに主人公に至ってはバツイチでギャンブル好き、ろくに働きもせず競馬で遊ぶ金を高齢の母の口座から勝手にお金を引き出すどうしようもないやつである。
しかし所々で現れる彼の人間味にはグッと引かれるものがある。
自分が信頼してる者に嘘をつかれゲームが不利な立場になっても相手を責めない、最初は信用してなかった相手でも仲間に入れてしまう、などなど人間らしさを最後まで決して失わない。
職も金もないダメなおじさんなのだが、人間にとって何が一番大切なのかを視聴者に教えてくれる存在なのだ。
ルールのシンプルさ
参加者は6つのゲームをし優勝を争うのだが、このゲームの内容は全て子どもの頃にやった遊びである。
- だるまさんが転んだ
- カルメ焼きの型抜き
- 綱引き
- ビー玉遊び
- 飛び石わたり
- イカゲーム
こういったジャンルの作品といえばルールが複雑で(それがシナリオのスパイスとなるのだが)、視聴者が100%理解できず置いてかれるというデメリットがある。
(個人的に映画ライアーゲームのファイナルは中盤からルールの解説が複雑になり理解度50%くらいで視聴していた)
しかしイカゲームでは子供が遊ぶゲームなのでルールが至ってシンプルなのだ。
・「だるまさんが転んだ」→鬼がこちらを向いてる時に動いたら脱落
・「型ぬき」→記号の形に綺麗に型抜きができなかったら脱落
・「つなひき」→10人対10人で戦い、負けた方が脱落
・「ビー玉遊び」→ルールは不問、手持ちのビー玉が無くなったら脱落
・「飛び石」→落ちたら脱落
・「イカゲーム」→イカゲームのルール通り負けた方が脱落
日本でもなじみのある遊びばかりでルールが非常にわかりやすいのである(イカゲームは韓国のものだが)
視聴者の”ルールをちゃんと把握しなければストーリーを理解できないストレス”が一切なくなるのだ。
画面の色彩と舞台セットのクオリティ

この作品の魅力の1つが映像の完成度だ。
まず、
画面を見ていて心地よい
ということである。
最初何故心地よいのか、恐らくそれは色のチョイスが視覚的に快感を覚えることなのだと思う。
・参加者が着ている緑のジャージと進行係のピンクのジャンプスーツ
・まるでテーマパークを連想させるポップな色合いの無数の階段
・チョコレートの箱のような、ピンクのリボンがかかった脱落者たちの棺桶
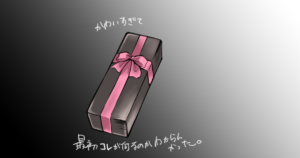
ストーリーがシリアスかつサスペンス要素もグロ要素も強い反面、画面が色彩が豊かかつポップでキュートなのでその温度差で
「私は今何の映画を見てるんだっけ・・・」
と一瞬我に帰ってしまった。夢を見ているような気分になる。
プラス、童心に戻るその空間だからこそその場で繰り返し起きる残虐なシーンも際立つのかと思う。
そして驚いたのが3つ目のゲーム「綱引き」以降から舞台のセットがさらに本格的なものになる。
綱引きの舞台に上がるエレベーター内の時間や、一試合ごとに進行役が次の綱を準備する様子などまるで本当にその場にいるかのような臨場感がじわじわと伝わる。
また「飛び石渡り」のセットに関しては参加者の落下時にリアリティを出すために地上1メートル上にセットを作ったのだとか。
日本で同じような映画を作るにしてもここは確実に負ける部分だと思う。
そして極め付けは「ビー玉」のシーン。
ずるいよ、あれは・・・
平和な日本にいたら感じることのない国へのSOS
というわけでイカゲームの感想をだらだらと綴ってみた。
正直昨今の日本の映画やドラマに全く興味を持たなくなっていた部分もあるせいか、より一層韓国の”ガチ度”に衝撃を受けたのかもしれない。
映画好きの友人にイカゲームの話をしたところ1つの結論がでた。
それは
・韓国の社会情勢が厳しいからこそ、作り手のメッセージ性が強くリアリズムを求めたものになる
・そしてこれは世界の視聴者へのSOSなのではないか
ということ。
日本は平和大国だ。
第二次世界大戦からしばらく経ち当時のことを実際に体験した方々も年々減りつつあり、戦争の悲惨さを直接知る機会がなくなってくる。平和な世はなるべくして当たり前に作られたと感じてしまう。
そして学歴が全てだった時代は変わりつつあり、学歴かかわらずあらゆる未来を選択できる時代になってきている。
日本の若者が政治に関心がない、という話は聞いたことがあると思うがそれはつまり
政治に関心を置かなくても平和な国だから
ということなのだろう。
平和な国にいるからこそ必死に生きることもなくなりあらゆる神経が麻痺していたのかもしれない。
- 一生懸命生きることってこうゆうことなのかも
- 人と人との繋がりってこうゆうことなのかも
- お金を失っても、最後まで失くしてはいけないものってこうゆうことかも
韓国社会を織り交ぜたただのデスゲームを観たつもりが人間の本質まで考えさせられてしまった。
ネットフリックスは決して安いわけではないが(月額1000円くらい)、日本の話題性だけで売ってる映画よりもずっとずっと観る価値があると思う。
シーズン2もかなり期待できるし、まだまだ繰り返し観続けていきたい作品である。
最後までお読みいただき感謝です。